こんにちは、ももです!☺️
早速ですが、
このように思ったことはありませんか?
紹介する習慣を身につけることで以下のメリットがあります。
これから紹介するものは、『7つの習慣』というベストセラーに書かれている習慣から抜粋したものです。著者のスティーブン・R・コヴィー博士は、過去200年の「成功に関する文献」を研究し、歴史から証明された「真の成功、永続的な幸福を得られる習慣」をこの本に綴っています。そのため確かな根拠がありますし、私の実体験も紹介していきます。
・幸せな人が実践している「人生の終わりから考える」習慣
参考文献
この記事では、著書「7つの習慣」を参考文献として取り上げています。
・著書『7つの習慣』:全世界で4000万部以上、日本では240万部以上販売されているベストセラー。20世紀にもっとも影響を与えたビジネス書の1位に輝いたこともある。
・著者スティーブン・R・コヴィー博士(1932ー2012):タイム誌が選ぶ世界で最も影響力のあるアメリカ人25人の一人に選ばれ、教育者やコンサルタント等として活躍。自分の運命を自分で切り拓くためのアドバイスを発信。
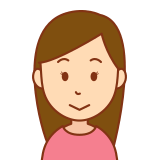
同級生も、芸能人も、なんで周りの人ばかり上手くいくんだろう…
私も幸せになりたいのに空回りしている気がする…😢

そんな時こそ、一度立ち止まってみよう😌
人生の最期を思い浮かべてみると、「自分だけの成功と幸せ」が見えてくるよ☺️
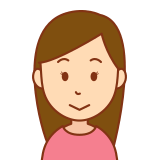
これまでも、どういう人生にしたいか考えたことはあったよ?
でも、結果が出ないから頑張るのが疲れたし、今のままでも悪くないか、、って変わらなくって。
そんな私でも上手くいく??

結果が出ない習慣は続かないよね😔
でも大丈夫!☺️✨️自分に合った成功&幸せな人生を思い描けることによって、日々が充実するし、結果が出るから習慣が長く定着するよ☺️
れから紹介する習慣には、たしかな根拠があるし私自身の実体験もあるよ。それでは伝えていくね!
これから紹介するものは応急処置のテクニックではありません。時間がかかる一歩一歩地道な習慣です。
しかし、繰り返しの説明となってしまいますが、これから紹介するものは、『7つの習慣』というベストセラーに書かれている習慣から抜粋したものです。
著者のスティーブン・R・コヴィー博士は、過去200年の「成功に関する文献」を研究し、歴史から証明された「真の成功、永続的な幸福を得られる習慣」をこの本に綴っています。
習慣を深く理解して実践していくと、不思議なくらい少しずつ自分が変わっていきました。『気づいたら前より、人生が充実しているし人に優しくなれている』って成長できています。結果的に、それが人生を変える一歩になっているんですよね。
私の場合、習慣を見直したことで“イライラや嫉妬”から抜け出せた実感があります。だから、この記事を読んでくれているあなたにとっても人生を変えるきっかけになると思うんです☺️ぜひ最後までご覧ください。
1.結論:幸せな人が実践している「人生の終わりから考える」習慣
人生の最期を思い浮かべることから始める
著書「7つの習慣」では第2の習慣として紹介されているものです。
2.習慣を身につけることで得られるメリット
3.習慣を身につける前の状況
3‐1.私を取り巻く環境

習慣を理解するために鍵となる「原則」と「パラダイム(もののみかた)」について説明するよ。

まずは根拠となる一説と著書「7つの習慣」から紹介するね。
さらにもう一つ、著書『7つの習慣』から私の人生観を変えた内容をご紹介します。
成功をテーマにした書籍を200年さかのぼって調べていくうちに、はっきりとしたパターンが見えてきた。最近の50年間に出版された「成功に関する文献」はどれも表面的なのだ。
そこに書かれているのは、社交的なイメージのつくり方やその場しのぎのテクニックばかりだ。
これとはまるで対象的に建国から約150年間に書かれた「成功に関する文献」は、誠意、謙虚、誠実、勇気、正義、忍耐、勤勉、質素、節制、黄金律など、人間の内面にある人格的なことを成功の条件に挙げている。
この人格主義が説いているのは、実りある人生には、それを支える基本的な原則があり、それらの原則を体得し、自分自身の人格に取り入れ内面化させて初めて、真の成功、永続的な幸福を得られるということである。
完訳7つの習慣 人格主義の回復 著者:スティーブン・R・コヴィー

難しいよね😓具体例を交えて分かりやすく伝えるね!
人はこれまでの経験や知識から様々な『もののみかた』をしています。
たとえば、成功の定義について尋ねた時に↓のような回答が返ってきたとします。
それぞれどのような『もののみかた』をしているかというと
同じものごとでも、『もののみかた』が違うと、『行動』が変わる。
『行動』が変われば『結果』が変わる。
たとえば、上司から残業をお願いされたとします。
- 『お金中心』の人は、喜んで長く残業するかもしれない。
- 『仕事中心』の人は、“評価を上げる出世のチャンス”と捉えて残業するかも知れない。
- 『家庭中心』の人は、最低限の仕事をして切り上げるか、他の人に頼んで断るかも知れない。
こうやって人生がつくられていきますよね。
著書では、
- 『もののみかた』のことを『パラダイム』
- 『もののみかたを変えること』を『パラダイムシフト』と呼んでいます。
「原則」は、『パラダイムシフト』をするときに、軸にすべきものです。
たとえば「誠実」「貢献」「可能性」「成長」など、“人格”をかたちづくるもの。歴史上の偉人だったり、“人格者”と呼ばれている人は、『原則』を軸にもっていることが想像できますよね。
では上司から残業をお願いされた際に、「原則」を軸に置くとどのようになるでしょうか。
「原則中心」の人にとって仕事はこのような存在になります。
- 他の優先事項とバランスを取って時間を投じるもの
- 自分の才能を発揮できる場
- お金を確保する手段
私なら、
- 『家族』『友人』に迷惑をかけず、
- “今”“自分にしか”できないことであれば、
- 健康を害さない範囲で残業します。
それ以外の場合は、他の人に頼めないか声を掛けたり、後日こなすことにします。
原則を中心に置いて、その時々で最優先事項に取り組む柔軟さが大事ですね。
残業を断ると、(断って良かったかな…)ってモヤモヤしたり、無理に残業すると仕事が嫌になることもありますよね。
「原則中心」の生き方を実践し始めてから、自分の選択に後悔がなくなりましたし、人間関係も良好に維持できています👍️✨️さらに家族・友人・仕事などそれぞれにコミュニティに対して、バランスを取れるようになり、人生の充実感が上がりました☺️
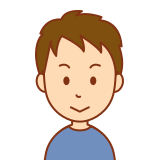

このあと、『原則以外』を中心にしていた私の過去について書いているよ。
必要な方だけ読んでいただければ大丈夫です。すぐに本題を知りたい方は「問題の明確化」から読んでね!😌
物心ついた幼少期〜学生時代は『家族(特に両親)』が私の人生の中心でした。
幼少期は家も食事もお金も、生きていくために必要な全てを親に頼るため、親に嫌われたら生きていけない😧のような生存本能もあったのかも‥と今は振り返ります。
両親、姉、私の4人で出かけていたときのエピソードを今でも鮮明に覚えています。大晦日、姉に除夜の鐘をつかせたかったらしく、母と姉は時間がかかっても行列に並ぶことを選びました。私は除夜の鐘に興味がなく飽きて帰りたかったのか駄々をこねたようです。母は私に素っ気なく姉と除夜の鐘をつきに行ってしましました。
悪かったのは私なのですが、母においていかれて強いショックを感じたことを覚えています。この時期に根付いた『家族(特に両親)』中心のもののみかたは、中学校や高校にも続き、心の不安定の原因の一つだったと振り返ります。
小学校3・4年〜26歳は『友人』が私の人生の中心でした。『友人』が中心となった経緯も鮮明に覚えています。
小学校で仲の良かったグループは私を入れて4人。私以外の3人は幼稚園が一緒。人見知りで人付き合いが下手だった私が3人の絆に入りこめず、ときどき“3人対私”の構図ができていました。
例えばバレンタインのチョコを一緒に作る話になったとき、そのうちの一人が『ももは呼びたくない。』とハブかれたことを覚えています。「もっと私が明るければ。もっと私が面白ければ、輪に入れてくれるかもしれない。」と友人の顔を伺い続けていました。
『友人』中心のもののみかたは、歳を重ねるごとに強まっていきました。高校3年生では仲の良かったグループメンバーと気まずくなり、素っ気ない態度を取られることが怖くて不登校になりました。
学校生活が世界の全てだと感じていた当時の私にとって、友人に嫌われたら生きていけない😔という思いから『友人』が私の人生の中心となっていました。
友人中心の考え方は、『7つの習慣』に出会う26歳まで、つまり中学、高校、社会人と友人の輪が広がっていってもなお続きました。
今なら友人とも良い距離感で付き合えますが、当時は
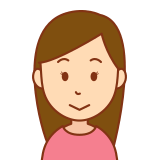
友人が優しい→私に価値がある⭕️
友人が冷たい→私に価値がない❌️
という不安定すぎる心で生活していました。そもそも、友人は冷たくしたつもりがない(私が被害妄想してしまっている)ときもあります。『友人』は人生においてとても大切な存在ですが、友人中心の人生では心が安定することは無いことを実感しました。
中学校〜専門学校は『所有物』中心でした。所有物には、
①有形物(家、車など)
②無形物(社会的地位や自分の評価)
がありますが、私は②の社会的地位や自分の評価を気にしていました。
なぜなら、中学校にあがり成績上位をとって周りから一目置かれるようになったり、生徒会に入れて、そこではじめて「自分の居場所」を得られたと感じたからです。
高校に上がると成績は維持できなくなり生徒会にも入らず、心の安定は崩れました。
高校3年生では難関の国立大学を目指していました。匿名のクラスの模試成績一覧から私の順位を当てた友人に本気でキレた覚えがあります。悪い成績を取った悔しさと、そんな成績がバレた恥ずかしさがあったためです。(その時の友人ごめんなさい🙇♀️)。
社会的地位や自分の評価はときにより変化していきますよね。変化するものを中心に持った結果、心は安定しませんでした。それだけでなく、自分より良い評価をもらっている人に嫉妬や敵対心を持ってしまい、人間関係はこじれる一方でした。
就職〜26歳は『配偶者』中心のもののみかたしていた時間もあります。
親や友人関係において、100%思い通りにはいかなかった私が、はじめて素の自分を認めてくれたと感じたのが今の旦那です。甘えに甘えて、旦那の気持ちに配慮せず思ったことは良いことも悪いことも全て口に出す、それを咎めることなく受け入れてくれる、そんな関係が楽でしたし、振り返れば依存状態だったと思います。
しかし旦那も人間でありその時々の事情や感情があります。旦那に少しでも冷たくされたように感じるとショックを受けました。冷たく感じたのは仕事で疲れていて口数が少なかっただけだったのですが、(怒らせた?嫌われた?)と不安になっていました。
自分のやってみたいことがあっても、旦那に少し反対されると(旦那に反対されたから辞める…)と主導権を放棄していました。
今なら長い期間をかけて自分のやりたいことを旦那に理解してもらうための努力をできます。しかし当時は旦那の存在は絶対だったため、心は不安定なまま、自分の人生を旦那に預けているような状態でした。
また、相手の考えに考慮せず自分の気分が良くなるために思ったことを全て口に出すという考え方は『自分』中心のもののみかたになっています。いわゆる“じこちゅう”状態ですね。
相手にのみストレスをかけ続ける関係が長く続かないことは一目瞭然ですよね。
就職後は『敵』中心のもののみかたをしていた時期もあります。
職場で苦手が上司が数人おり、職場でも家に帰ってからも上司のことが頭から離れず、『敵』認定していました。
敵対している相手に同じく批判的な人を見つけると安心し、自分を正当化していました。
上司との関係が上手くいかず社労士の先生に介入してもらったこともあります。これだけ大きな問題になるほど、『敵』中心の考えが根付いていたのだな、と振り返ります。
読んでいる方も想像してもらえるかと思いますが、『敵』を人生の中心にしていて良いことは一つもありませんでした。仕事がやり辛い、仕事に行くのが嫌になる、プライベートも心から楽しめない状態でした。
高校からスマホを持ってから『娯楽』中心のもののみかたをしていた時期もあります。
現実に疲れていた私は、傷つくことなく楽しませてくれるスマホに依存しました。学校や職場以外ではスマホを肌見放さず(トイレやお風呂にも)アニメやYouTubeを見続けました。
受験時期に勉強に集中できなかった理由の一つはスマホ依存にあると振り返ります。
スマホで楽しい時間を過ごしても現実では問題は解決しません。一人で快楽を追求し続ける時間に、本当の意味で幸せを感じることはありませんでした。一人でスマホに向き合った何千・何万時間は、楽しいけど満たされない時間でした。
3‐2.問題の明確化
問題として以下2つがあげられます。
- 人生の最期を考えたことがなかったこと。
- 『原則以外』を人生の中心としていたこと。

上で紹介した『家族』『友人』『所有物』『配偶者』『敵』『娯楽』『自己』の他に、
『仕事』『お金』『協会』『原則』の合計11個が、人が一般的に持つ中心として紹介されているよ。

『原則以外』を人生の中心に置いていた結果、
という結果になったよ。
『
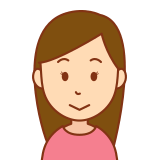
『原則』以外は、変化するものなんだね。
だから、人生の中心に置いてしまうと、成功や幸せが長続きしないんだね🤔

そのとおり💡
れでは、サクッと問題を解決して
状態を一緒に目指していこう!
大丈夫、実践すれば誰でもすぐに効果が感じられる習慣だよ!☺️
4.終わりを思い描くことから始める
4-1.7つの習慣の考え方

まずは根拠となる一説を、著書『7つの習慣』から紹介するね。
人生が終わるときをありありと思い描き、意識することによって、あなたにとってもっとも重要な基準に反しない行動をとり、あなたの人生のビジョンを有意義なかたちで実現できるようになる。
完訳7つの習慣 人格主義の回復 著者:スティーブン・R・コヴィー
4-2.「終わりを思い描くことから始める」ための3ステップ

「終わりを思い描くことから始める」ための3ステップは↓の通りだよ!
- 自分のお葬式を想像する
- ミッションステートメントを書く
- ミッションステートメントに沿って行動する
①自分のお葬式を想像する

具体的には
- 大切な人たちから自分の人生をどのように語って欲しいか?
- どういう貢献や功績を覚えていてほしいのか?
- 大切な人達にどう影響を及ぼしたいのか
を想像していくよ。
私が考えた、大切な人達から語って欲しい内容を一部紹介するね。

いきなり、自分のお葬式と言われても難しいかもしれない。
私も最初はピンとこなかった。でも、誰しも人生でやってみたいこと、達成したいことはあるはず。そのまま素直に紙やスマホのメモに書いてみよう。
考えは日々変わると思うから、その都度修正していけばOK!
②ミッションステートメントを書く

ミッションステートメントとは、自分自身の憲法だよ。想像するお葬式のイメージに近づけるように、『自分はこういう考えを持つ。』『自分はこういう行動をする。』と自分だけの憲法をつくるの。

ミッションステートメントを書くにあたって、重要なものが【原則】
自分の夢や目標を【原則】に調和させることが不可欠。
なぜ自分の夢や目標を原則に調和させることが不可欠かについて説明します。
原則は、『パラダイムシフトを行うときに軸とするべきもの』と先ほど説明しましたね。言い方を変えると、迷った時に行動を良い方向へ導く指針になります。
たとえば、旅行でゴールに到着するためには、
- 現在地
- 正しい地図
- 正しい方向を導く指針(羅針盤など)
が必要ですよね?
人生についても同じです。人生におけるゴール(夢や目標)に到着するための“正しい方向を導く指針(羅針盤)となってくれるのが『原則』です。
『原則』という指針を持つことによって“成功&幸せなゴール”までどれほど距離があるか、またゴールまでの具体的な道のりが見えてきます。つまり、現在地&正しい地図が見えてきますよね。
👉️結果、ゴール(夢や目標)に到着できます。このように歩み続けた結果、人生における『真の成功、幸福』を永続的に手に入れられると著者は語っています。私自身も実体験をもって同意します。

じゃあ実際に作ってみよう!☺️

さっき考えた、お葬式で大切な人から語って欲しい内容を思い出してみよう!
それが今の自分が叶えたい夢や目標だね。
その夢や目標は、何が中心になっているかな?
たとえば↓は、家族・友人が中心になっているよ。
家族には、良い理解者であったと語って欲しい。家族一人一人の価値観、夢、目標、問題を理解し、夢や目標は一緒に叶え、問題は当人が主体的に解決できるように1ピースになりたい。最期は子どもと穏やかな時間を過ごしたい。
実際にノートなどに書いてみよう🖋️⭕️

次に、『原則』と調和させるよ。
私は、
個人👉️『可能性』『成長』
他者関係👉️『誠実』『シナジー』
という原則を軸に置いているよ。

著書では、その他に
謙虚、勇気、正義、忍耐、勤勉、質素、節制、黄金律、貢献、尊厳
など紹介されているから、気になったら読んでみてね。
自分に合った原則を軸に置いてみよう!
家族には、良い理解者であったと語って欲しい。家族一人一人の価値観、夢、目標、問題を理解し、夢や目標は一緒に叶え、問題は当人が主体的に解決できるように1ピースになりたい。最期は子どもと穏やかな時間を過ごしたい。
➕️原則=『可能性』『成長』『誠実』『シナジー』
⇓

同じように例を2つ作ったみたから、参考にしてね☺️
例①
仕事では、過去の自分と同じように悩んでいる人に対して、人間関係改善のサポートがしたい。家族・友人、身近にいる人をまず助けられるような優良コンテンツをつくりたい。
➕️原則=『可能性』『成長』『誠実』『シナジー』
⇓
例②
- 経済的に自立したい。会社に縛られない自由を手に入れる(集まりたいときに帰省ができたり地元の友人と集まれる環境をつくりたい。)
- 子育てで収入減の間も在宅でできる安定した副収入がほしい。
- 子育て中も家族と旅行や外食など過ごせる時間の選択肢を増やしたい。
➕️原則=『可能性』『成長』『誠実』『シナジー』
⇓

一度作って終わりではなく定期的に見直すことも大事。
私は週に一度、内容や言葉のニュアンスを見直すようにしていて、自分の信念がより明確&統一されたものになっているよ。定期的に見直すことで、初心も忘れないしモチベーションも維持できるよ。
③ミッションステートメントに沿って行動する

を実施したよ。高校女子のクラスメイトに呼びかけて同窓会を開いたよ!
それぞれの近況や今の悩み、夢、何気ない話題を気兼ねなく話すことができた😌集まったそれぞれが、充実感を持って幸せな時間を過ごすことができたと思う!
次の同窓会をいつしようか、話があがっているよ💡
人間関係の充実を記したミッションステートメントを実施した結果、有意義で幸せな時間を送ることができた😌✨️
大切な学生時代の仲間と定期的に同窓会を開けている、という状態は、私にとって成功&幸せな人生だと感じるよ☺️
『原則』を軸においた選択だからこそ、自分の選択に後悔なく迷いなく行動できるよ。
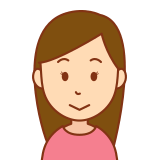
こうやって、行動の一歩を踏み出していけばいいんだね。

私も実践しながら成長してるところだよ☺️だから、この記事を読んでくれている皆と成長していきたいなと思ってる☺️
最初はうまくできないこともあったけど、歴史から証明された人生がうまくいく習慣だから、続ければ成果が出る!と安心して習慣を続けられるんだ◎
5.結果、変化
5-1.自分に合った、成功&幸せな人生を思い描ける→日々が充実する
5-2.迷ったときに正しい道筋が見える
『原則』中心に過ごすことでトラブルからV字回復し、円満退職をすることができました。
諸事情あり急に退職することになりました。私は、日々の業務+引き継ぎ業務で、責任+残業のキャパオーバーが起こりました。結果メンタルが崩れ上司に感情的に当たってしまった結果トラブルを起こしてしまいました。このときの私は『自分』『敵』中心のもののみかたをしていました。
『原則』中心のもののみかたによって状況が好転しました。
『原則』の中でも特に『誠実』が私を助けてくれました。まず、上司に対して潔く、言い訳なく、謝罪を行いました。
上司との関係はここで改善しました。『誠実』という自分にブレない軸ができたからこそ、今まで見えてこなかった上司の立場が見えてきました。
私が退職することで、上司の身体的・精神的負担が跳ね上がります。またその職場において私が一番長く務めていたため、上司も分からない業務があり不安が大きかったと思われます。
そのため、上司から任されていた業務マニュアルは、できる限り詳細に、残る人が使いやすい内容に修正しました。
退職後もその上司とは穏やかに連絡を取り合える関係を築けています。最期まで誠実さを持って仕事に取り組んだことで、トラブルからV字回復し円満退職することができました。
5-3.人間関係が充実する
5-4.効果が出るため習慣が長く定着する
6.まとめ
幸せな人が実践している「人生の終わりから考える」習慣をお伝えしました。
「終わりを思い描くことから始める」ための3ステップ
- 自分のお葬式を想像する
- ミッションステートメントを書く
- ミッションステートメントに沿って行動する
続けることで⇓のメリットがあります✨️
一度は誰しも経験のある悩みではないでしょうか。ぜひ実践して効果を感じてもらえると嬉しいです☺️✨️
7.さいごに
7‐1.このブログを読んでくださっているあなたへ
もしこの記事があなたが少しでも前に進むヒントになれば嬉しいです💡
これからも少しでも皆さんの悩み解決の1ピースとなれるようにブログを書いていきたいと思います。このブログが、人間関係の悩みを解決できる場であること、また皆の憩いの場となれるよう努力していきますのでよろしくお願いします☺️
7-2.これまで関わってきた方々へ
これまで、たくさん心配をかけたり迷惑をかけてしまったこともあったと思います。そんな私と関係を続けてくれて本当に感謝しています。これからは、過去の経験を活かして、新しい価値を提供できる人になりたいと思ってます。お互いに有意義な人生になるよう、一緒に歩んでいけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします🙇♀️


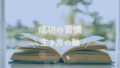
コメント